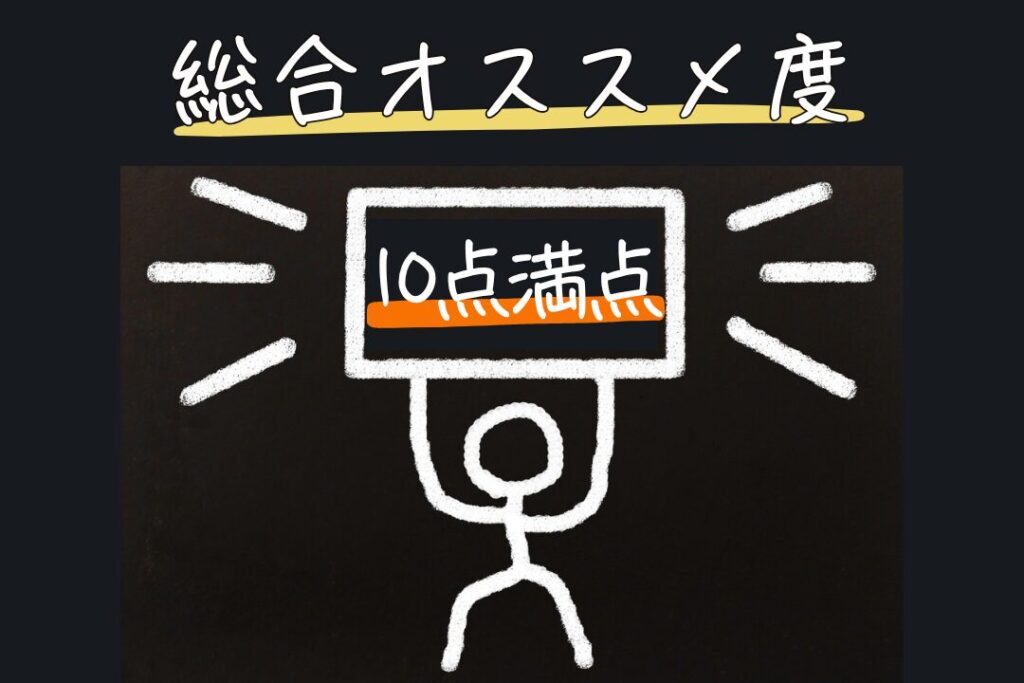日本酒のラベルで時折見かける「生酛(きもと)」「山廃酛(やまはいもと)」そして、特に記載がない場合に多く採用されている「速醸酛(そくじょうもと)」。
これらは日本酒の味わいを決定づける重要な要素、「酒母(しゅぼ)」別名「酛(もと)」の製法です。
「一麹、二酛、三造り」という酒造りの格言があるように、麹造りに次いで重要視されるのが、この酒母造りです。
酒母とは、文字通り「酒の母」であり、アルコール発酵を行う酵母を大量にそして純粋に培養する工程、またその培養液自体を指します。
この酒母の製法の違いが日本酒の風味や個性に大きな影響を与えるのです。
本記事では、これら3つの主要な酒母製法、「生酛」「山廃酛」「速醸酛」について、その製法の特徴、歴史、味わい、そして実売価格に至るまで、詳しく解説していきます。
それぞれの違いを理解することで、あなたの日本酒選びがより深くより楽しいものになることでしょう!
酒母(酛)とは?日本酒造りの心臓部

日本酒造りにおいて、酒母造りの主な目的は、アルコール発酵を担う優良な酵母を大量に育てることです。しかし、酵母を育てる過程では、日本酒にとって好ましくない野生酵母や雑菌も繁殖しやすい環境にあります。
そこで重要になるのが「乳酸」の存在です。乳酸は、酒母の環境を酸性にすることで雑菌の増殖を抑え、目的とする清酒酵母が優先的に増殖できる環境を作り出します。
この乳酸をどのように得るかによって、酒母の製法は大きく「生酛系酒母」と「速醸系酒母」の二つに大別されます。
生酛系酒母:酒蔵に生息する自然の乳酸菌を取り込み、育成することで乳酸を得る伝統的な方法。「生酛」と「山廃酛」がこれに該当します。
速醸系酒母:人工的に培養された醸造用乳酸を添加することで、迅速に乳酸環境を作り出す近代的な方法。「速醸酛」がこれにあたります。
現在、日本酒全体の製造割合で見ると、速醸酛が約90%、山廃酛が約9%、そして生酛は約1%と、手間のかかる生酛系は少数派となっています。
伝統製法「生酛(きもと)」- 自然の力を活かす究極の手仕事
生酛造りは、江戸時代から続く日本酒の最も伝統的な酒母の製法です。
製法と歴史
-.png)
生酛造りの最大の特徴は、「山卸し(やまおろし)」という作業です。これは、蒸した米、米麹、水を半切桶(はんぎりおけ)と呼ばれる浅い桶に入れ、蔵人が櫂(かい)という棒で米をすり潰し、粥状にする作業です。この重労働を低温環境で数回に分けて行うことで、米の糖化を促し、酒母を均質化します。
その後、酒蔵の環境中に自然に存在する乳酸菌を時間をかけて取り込み、その力を借りて乳酸を生成させます。この自然の乳酸菌が十分に増殖し、酒母が完成するまでには約1ヶ月という長い期間を要します。生酛造りは、酒蔵の壁、空気、仕込み水、さらには木製の道具などに生息する多様な微生物と共生しながら酵母を育てる、まさに自然の力を最大限に活かした製法と言えるでしょう。
味わいの特徴と魅力
生酛造りで育った酵母は非常に生命力が強く、アルコール度数が高くなる醪(もろみ)の末期までしっかりと発酵を続ける力を持っています。
これにより、雑味の原因となる物質が少なく、力強くキリッと締まった、それでいて深みのある味わいが生まれます。
- 濃厚で奥深いコクと、複雑な旨味。
- しっかりとした酸味がありながらも、スッキリとした後味。
- ヨーグルトのような乳酸由来の香りや、熟成によってさらに複雑な香りが生まれることもあります。
- 特に燗にすることで、その複雑な香りがより一層引き立ち、旨味が増します。
現状と課題
その製造には多大な手間と時間、そして高度な技術が必要とされるため、現在では生酛造りを採用している酒蔵は全体の約1%と非常に稀少です。
また、山卸しに使用される木桶のメンテナンスや、それらを扱える職人の不足も課題となっています。
実売価格例
大七 生酛 純米酒
720mlで約1,500円~2,000円程度。伝統的な生酛造りで知られ、豊かなコクと旨味が特徴です。

菊正宗 嘉宝蔵 灘の生一本 生もと純米
1800mlで約3,000円~4,000円程度。キレのある辛口ながら、生酛ならではの深みも感じられます。

澤乃井 生酛純米大吟醸 武陽
兵庫県特A地区産の山田錦を精米歩合35%まで磨いた最高級の純米大吟醸。 洋梨やメロンを思わせる華やかでエレガントな吟醸香と、生酛造りならではのなめらかな口当たりと奥深い旨味、繊細な酸が絶妙な味わいをみせてくれます。

「山廃酛(やまはいもと)」- 生酛の進化形、力強さと複雑味の調和
山廃酛は、「山卸廃止酛(やまおろしはいしもと)」の略称で、その名の通り、生酛造りにおける「山卸し」の工程を廃止(省略)した製法です。
製法と歴史
明治時代後期、麹の酵素力が向上し、また精米技術も進歩したことにより、山卸しを行わなくても米の糖化が十分に進むことが分かり、山廃酛が考案されました。
山卸しは行いませんが、生酛と同様に酒蔵に存在する自然の乳酸菌の力を借りて乳酸を生成させる点は共通しています。
麹の力で米を糖化させ、その糖分を酵母が利用してアルコール発酵を進めます。
酒母が完成するまでの期間は約1ヶ月と、生酛と同程度の期間がかかり、依然として手間と時間がかかる製法です。
山卸しをしない代わりに、櫂入れ(攪拌作業)の頻度や方法に工夫が凝らされますが、この櫂入れが生酛以上にハードな作業となる場合もあります。
これは、生酛は前半の山卸に手間がかかる分後半の撹拌作業が楽になりますが、山廃酛は山おろしがない分、ハードになるからです。
ただし、山廃の場合は使用する貴重な木桶のメンテナンスの手間などがないなどの大きなメリットがあります。(参照:SAKETIMES)
味わいの特徴と魅力
山廃酛で造られた日本酒は、生酛と同様に自然の乳酸菌由来の複雑な味わいやコクを持ちつつ、以下のような特徴が見られます。
- 生酛に比べて、より複雑味が増し、酸味の刺激が強い傾向があると言われます。これは仕込み温度の違い(生酛が約5℃に対し、山廃は約8℃など)や、山卸しをしないことによる米のデンプンの状態の違いなどが影響すると考えられています。
- 濃厚で飲みごたえのある豊かな味わいと、しっかりとした酸味が特徴。
- 時には「いぶしたような」独特の香りが感じられることもありますが、近年の衛生管理が徹底された醸造では、この香りは抑えられる傾向にあります。
- 燗にしても美味しく、また常温でもその複雑な風味を楽しめます。
現状
山廃酛で造られる日本酒は、全体の約9%を占めています。
実売価格例
天狗舞 山廃仕込純米酒
720mlで約1,500円~1,800円程度。山廃造り特有の濃醇な旨味と酸味が特徴です。

菊姫 山廃純米
山廃仕込みの先駆者的存在で、昭和58年に日本酒業界初となる「山廃仕込」と表示した純米酒として発売されました。
720mlで約2,000円~2,500円程度。
ナッツやカラメルを連想する芳醇な香りと力強い酸味と米のたっぷりとした旨味を楽しめるお酒です。熟成によってさらに深みを増す、骨太な味わいです。

遊穂 山おろし純米
720mlで約1,800円~2,000円程度。濃醇で旨味のある、調和のとれた酸が特徴で、濃すぎず、軽すぎず、食中酒として絶妙なバランスのお酒です。

爽やかで甘い香りが漂い、口中ですぐに広がる濃醇な味わいと綺麗な酸立ちが特徴。雄町らしい旨味もしっかり。アルコール度数の高さを感じさせない味わいながらも、生原酒の力強さとフレッシュさもしっかりと楽しめます。冷蔵庫で2年3年と熟成させることも可能。じっくり楽しみたいお酒です。
▶︎ 詳しくはこちらの記事をご覧ください >>
京都・木下酒造が醸す「玉川 自然仕込 山廃純米酒 雄町 無濾過生原酒」を徹底解説! 雄町米と山廃仕込みが織りなす濃厚な旨味と複雑な味わい、料理との相性、実売価格まで、この冬季限定酒の魅力を余すことなくお届けします。
近代製法「速醸酛(そくじょうもと)」- 安定と効率、クリアな味わいの追求
速醸酛は、明治43年(1910年)に国立醸造試験所(現在の酒類総合研究所)の江田鎌治郎(えだかまじろう)氏らによって開発された、近代的で効率的な酒母の製法です。
製法と歴史
速醸酛の最大の特徴は、酒母を仕込む初期段階で、あらかじめ純粋培養された醸造用の「乳酸」を直接添加することです。
これにより、酒母タンク内のpHを迅速に下げて酸性状態を作り出し、雑菌の汚染リスクを大幅に低減させることができます。
乳酸菌が乳酸を生成するのを待つ必要がないため、酒母造りの期間は約2週間程度と、生酛系に比べて半分以下に短縮されます。
これにより、安定した品質の酒母を効率的に、かつ失敗のリスクを抑えて造ることが可能となり、現在では日本酒全体の約90%がこの速醸酛で造られています。
日本酒のラベルに「生酛」や「山廃」といった表示がないものは、基本的にこの速醸酛で造られていると考えてよいでしょう。
味わいの特徴と魅力
速醸酛で造られた日本酒は、一般的に以下のような特徴を持ちます。
- 雑味が少なく、クリアでスッキリとした淡麗な味わい。
- 酵母本来の特性がストレートに現れやすく、吟醸香などのフルーティーで華やかな香りが引き立ちやすい。
- 軽快で飲みやすく、初心者にも親しみやすい味わいのものが多い。
- 品質が安定しており、比較的リーズナブルな価格帯の製品が多いのも魅力です。
実売価格例
獺祭 純米大吟醸45
特に海外で評価を上げている獺祭。720mlで約2,200円~3,000円程度。華やかな香りと綺麗な味わいが特徴のお酒です。

八海山 特別本醸造
720mlで約1,200円~1,500円程度。やわらかな口当たりと淡麗でスッキリとした辛口が特徴。冷でよし、燗でよしで、食中酒としても人気です。
久保田 千寿 吟醸
720mlで約1,300円~1,600円程度。穏やかで上品な香りと飲み飽きしない綺麗でスッキリとした味わいが特徴で、食事と楽しむ吟醸酒。喉をさらっと通るキレの中に、米本来の旨味と酸味が感じられるお酒です。

▶︎ 他の日本酒に興味がある方はこちらから >>
色んな日本酒の実飲レビューをしています。美味しい日本酒を見つけてくださいね!
三者比較:あなたに合うのはどの酛?
| 特徴 | 生酛 | 山廃酛 | 速醸酛 |
| 乳酸取得 | 自然の乳酸菌を育成 | 自然の乳酸菌を育成 | 醸造用乳酸を添加 |
| 山卸し | あり | なし | なし |
| 製造期間 | 約1ヶ月 | 約1ヶ月 | 約2週間 |
| 味わい傾向 | コク深く複雑な味わい。スッキリとしたキレがありつつも濃醇な味わい、力強い余韻 | 生酛造りに比べ、まろやか。旨味のあるふくよかで飲みごたえのある豊かな味わい | 淡麗、クリア、スッキリ、フルーティー |
| 酵母の強さ | 非常に強い | 非常に強い〜強い | 穏やか(安定) |
| アミノ酸量 | 多い傾向 | 多い傾向 | 比較的少ない |
| 主な香り | ふくよかな香り、クリーミーな香り、香木のスパイシーな香りなど、複雑で奥行きのある香り | 生酛に比べると香りは穏やかだが、旨味や酸味を感じさせる香りが特徴 | 酵母由来の華やかな香り(吟醸香など) |
| 価格帯 | 比較的高め | 比較的高め | 比較的リーズナブルなものが多い |
| 生産割合 | 約1% | 約9% | 約90% |
生酛・山廃酛の現在と未来
手間とコストがかかるため少数派となった生酛系酒母ですが、近年、その複雑で豊かな香味を求める声や、伝統的な製法への関心から、あえて生酛や山廃酛に取り組む酒蔵が再び注目されています。
これらの日本酒は、個性的な味わいを持ち、和食だけでなく、中華料理や西洋料理など、幅広いジャンルの料理とのペアリングの可能性も秘めています。
消費者としては、「生酛だからこういう味」「山廃だからこう」といった固定観念に縛られず、それぞれの日本酒が持つ多様な魅力を発見していくことが、日本酒をより楽しむための秘訣と言えるでしょう。
まとめ
「生酛」「山廃酛」「速醸酛」は、それぞれ異なる歴史的背景、製造プロセス、そしてそれがもたらす独特の味わいを持っています。
- 生酛は、自然の力を最大限に活かした伝統の技が生み出す、力強く奥深い個性的な味わい。
- 山廃酛は、生酛の精神を受け継ぎつつ、乳酸発酵をじっくりと行うことにより香りは控えめだが、飲みごたえのある豊かな味わい。
- 速醸酛は、近代的な技術により安定した品質とクリアで香り高い飲みやすい味わい。
どの製法が優れているということではなく、それぞれに独自の魅力と価値があります。
ご自身の好みや、合わせる料理、楽しみたいシーンなどを考えながら、これらの「酛」の違いを意識して日本酒を選んでみてはいかがでしょうか。
きっと、新たな日本酒の扉が開かれるはずです。
【関連記事】