
石川県白山市、霊峰白山の麓に広がる手取川扇状地。この豊かな自然に恵まれた地に、1870年(明治3年)創業の老舗酒蔵「吉田酒造店」はあります。
代表銘柄「手取川」で知られ、150年以上にわたり高品質な日本酒を醸し続けてきました。
伝統的な技術を守りながらも、時代の変化に対応した革新的な酒造りに挑戦し、特に40代・50代の日本酒愛好家から注目を集めています。この記事では、吉田酒造店の歴史、酒造りの特徴、そして未来を見据えた取り組みについて詳しくご紹介します。
吉田酒造店の歴史とテロワール
吉田酒造店が位置する白山市は、白山からの清澄な空気と、手取川がもたらす豊かな伏流水に恵まれた土地です。蔵の代表銘柄である「手取川」の名は、この地域を流れる一級河川「手取川」に由来します。
かつては「暴れ川」として知られた手取川ですが、金沢平野の水源として地域の米作りを支え、吉田酒造店の酒造りに欠かせない良質な水をもたらしています。
手取川の名前の由来には次のような由来があります。
源平の戦で木曽義仲が南進していたとき大きな川に出くわし、なかなか渡れないので武士たちが互いに手を取り合い渡ったことから手取川の名が付いたとされる。
引用:ミツカン水の文化センター
 kimi
kimi 手を取り合ったことが手取川の由来・・・。素敵な話ね!
150周年を迎えるにあたり、次の言葉を発信しています。
1870年に創業し、幾多の困難に遭遇しながらも酒造りを続けてこられたのは、
引用:吉田酒造店
先代達の努力はもちろんですが、酒販店の皆様や地域の皆様、そして何よりも支えていただいたお客様のおかげです。
 Ryo
Ryo 手取川の名前の由来の如く、手を取り合って150年の歴史を紡いできたんだね!
現在は7代目蔵元・吉田泰之氏が、伝統を受け継ぎながらも新たな挑戦を続けています。
吉田氏は東京農業大学を卒業後、山形県の銘醸蔵「出羽桜酒造」で修業し、実家に戻ってからは先代杜氏である山本輝幸氏のもとで地域に適した酒造りを学び、杜氏に就任しました。
吉田酒造店の酒造りの特徴
吉田酒造店の酒造りは、伝統と革新が見事に融合しています。
伝統技法「山廃仕込み」へのこだわり
石川県の能登杜氏が得意とする伝統的な技法「山廃仕込み(山廃酛(やまはいもと))」は、吉田酒造店の酒造りの大きな特徴です。
「麹」の力によって米のでんぷんが糖に変わり、糖が酵母に働きかけることでアルコール発酵を促す、「生酛造り(生酛(きもと))」の一種で、「山卸(やまおろし)」という蒸し米や麹を、櫂(かい)という棒のようなものですりつぶす作業を省略したものを「山廃仕込み(山廃酛(やまはいもと))」と言います。
自然界に存在する乳酸菌を利用して酒母を育てるこの方法は、乳酸を添加してアルコール発酵を促す「速醸造り(速醸酛(そくじょうもと))」に比べると、腐りやすいという欠点があります。
腐りやすく、雑菌対策や温度管理など手間暇がかかるものの、複雑で奥行きのある味わいを生み出します。
その一方で「造り手である杜氏の長年の経験と高度なセンスを要求され (中略) 手間もかかるために敬遠される傾向もあり、(中略) 山廃で仕込まなくなった酒蔵も多い
」(引用:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)のも現状です。
そのように手間暇やリスクのある製造法ですが、吉田酒造店では、麹室に入る際に作業着や帽子を着替えるなど、雑菌の侵入を徹底的に防ぐことで、安定した「山廃仕込み」を可能にしています。
地元産原料へのこだわり
「ここでしか造れないお酒」、すなわち地元・石川県白山市を表現する酒造りを目指し、原料米の多くに地元産を使用しています。
石川県独自の酒米「石川門」や「百万石乃白」をはじめ、「五百万石」なども使用。
特に「石川門」は扱いが難しいとされる米ですが、蔵人たちが研究を重ね、その特性を活かした優しい甘みのある酒を生み出しています。
「石川門」の取り扱いの難しさを吉田酒造店では次のように表現しています。
プリンセスのような繊細さ。
引用:吉田酒造店
石川県で開発された、まるで「プリンセス」のような酒米。お米を蒸す際に非常に割れやすく、どの酒米よりも菌に敏感なので徹底的にケアしないと香りが悪くなることも。これでもかと可愛がらないとヘソを曲げてしまう「プリンセス」は、その特有の繊細な甘みで、まろやかな味わいのお酒に。
現在、使用する米の約8割は地元・白山産となっています。仕込み水はもちろん、白山の伏流水を使用しています。
最新技術の導入
例えば、「回転式自動洗米浸漬装置」は、米の表面の糖分を丁寧に取り除き、吸水率を厳密に管理することで、蒸米の品質を高め、原料米のポテンシャルを最大限に引き出すことに貢献しています。
二蔵制度による切磋琢磨
吉田酒造店の特徴の一つが、1997年から始まった二蔵制度です。
山本輝幸杜氏と吉田行成杜氏という二人の杜氏がそれぞれ「山本蔵」と「吉田蔵」を率い、互いに競い合うことで日本酒造りのさらなる高みを目指してきました。
「山本蔵」が造る「手取川」と、「吉田蔵」が造る「吉田蔵」は兄弟銘柄として知られ、それぞれ異なる個性を持っています。特に純米大吟醸を飲み比べることで、その違いを楽しむことができます。
また、近年はそれぞれのブランドコンセプトを明確化する流れを作っているようです。そのことについて、吉田酒造店 代表取締役の吉田泰之さんはSAKE TIMESのインタビューで次のように語っています。
「吉田蔵」を”真の地酒”を目指す銘柄へとシフト。酒蔵のある地域で育てた酒米と白山から流れる仕込み水、金沢酵母を用い、さらに能登杜氏が得意とする山廃仕込みを採用して、地元の素材や技術に特化したブランドへと切り替えました。」
引用:SAKE TIMES
代表銘柄と革新的銘柄
吉田酒造店は、伝統的な銘柄から革新的な銘柄まで、多彩なラインナップを誇ります。
代表銘柄「手取川」
吉田酒造店の代表銘柄「手取川」は、地域とのつながりを大切にした日本酒です。吉田酒造店の代表銘柄であり、「喜んでもらえる酒を産み出すことに徹する」という蔵元の想いが込められています。
特に「山廃仕込み」の技術が光る純米酒は、柔らかな酸味と繊細な旨味のバランスが絶妙で、多くの日本酒ファンに愛されています。
飲み方は冷やから熱燗まで幅広い温度帯で楽しめるのも特徴です。
冷や〜常温ではフルーティーさを感じることができ、熱燗ではキレ良さとお米の旨味を強く感じられます。
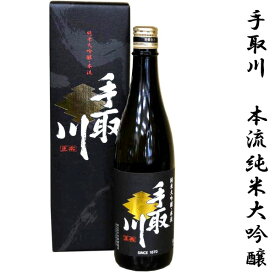
革新的銘柄「吉田蔵u」(モダン山廃)
「吉田蔵u」は、創業151年目に7代目蔵元・吉田泰之氏が「真の地酒」を目指して立ち上げた新しいブランドです。
伝統的な山廃仕込みをベースにしながらも、独自研究して開発した「モダン山廃」というコンセプトで醸されています。
「モダン山廃」の特徴を吉田酒造店では3つ挙げています。
① フレッシュな酸味と爽やかな旨味
② 発酵由来の微発泡感
③ 飲み疲れしにくいアルコール13%以下の無濾過原酒ナチュラルで優しい味わいを感じてください。
引用:吉田酒造店
原料には石川門や百万石乃白といった地元米と、代々受け継がれてきた自社培養の金沢酵母、手取川の豊かな伏流水、蔵付きの乳酸菌を使用し、人工乳酸や酵素剤などの添加物は一切使用しない土地のテロワールを生かしたナチュラルな造りを徹底しています。
「吉田蔵u」(モダン山廃)の軽やかでフレッシュな味わいは、普段日本酒をあまり飲まない層や若い世代からも支持を集めています。
石川県の在来米で、コシヒカリの最古の先祖とも言われる「巾着」を使った限定酒や、貴醸酒タイプなどもリリースされています。


未来へ繋ぐ、持続可能な酒造り
吉田酒造店は、気候変動への危機感を背景に、「ミライへ繋ぐ、持続可能な酒造り
」(引用:吉田酒造店)を重要なテーマとして掲げ、具体的なアクションを起こしています。
地元農家との連携強化「酒米振興会」
2014年に地元の農業を守るため「山島の郷酒米振興会」を設立。
現在は約40軒の契約農家と協力し、酒米栽培に取り組んでいます。
蔵人も春から秋にかけて田植えや稲刈りに参加し、米作りへの理解を深めています。
農家と酒蔵が二人三脚で米作りと酒造りに取り組むことで、互いの知見を共有し、品質向上に繋げています。
冬には酒米振興会の若手農家が酒造りに参加することもあるそうです。
再生可能エネルギーへの転換
2021年5月より、蔵で使用する電力を100%再生可能エネルギーに切り替えました。
さらに、自社田に垂直型のソーラーシェアリング設備を設置し、発電した電力を自家消費しています。
これによりCO2排出量を削減し、環境負荷の低減に努めています。
地域環境保全への貢献
地元の「白山手取川ジオパーク」と連携し、売上の一部を白山の環境保全活動に寄付しています。
また、「白山の光と影」をテーマにしたフォトコンテストを実施するなど、地域の自然環境の現状を伝える活動も行っています。
災害時には、ソーラーシェアリング設備による緊急用電源や、酒造用の水源(製造期間中)を地域に提供することも検討しており、地域防災への貢献も視野に入れています。
吉田氏は「地元のものにこだわると、地域内で循環が起こる。物流の距離も短くなり、消費者の方々も『地元の自然を大切にしていこう』と意識してもらうことで、環境に優しい行動が増え、持続可能な社会につながっていくと期待しています
」(引用:SAKE TIMES)と語っています。
これらの取り組みは、単なるプロモーションではなく、本質的な活動として継続していくことを目指しています。
国際的な評価と文化発信:映画「The Birth of Saké」
吉田酒造店の伝統的な酒造りと蔵人たちの営みは、日系アメリカ人監督エリック・シライ氏によってドキュメンタリー映画「The Birth of Saké(酒の誕生)」として記録されました。
144年間変わらぬ手法で酒造りに向き合う職人たちの姿を美しく捉えたこの作品は、2015年のトライベッカ国際映画祭で審査員特別新人監督賞を受賞するなど、海外で高い評価を受けました。
この映画は、日本の伝統文化である酒造りの魅力を世界に伝え、日本酒の普及に大きく貢献しました。
蔵元での楽しみ方
吉田酒造店では、直売スペースが設けられており、「手取川」や「吉田蔵u」をはじめとする様々なお酒の試飲や購入が可能です。
ただし、残念ながら酒造見学は行っていないようです。
訪問の際は、事前に営業状況などを確認することをおすすめします!
吉田酒造店所在地
〒924-0843 石川県白山市安吉町41
TEL:076-276-3311(代) / FAX:076-276-3378
まとめ:40代・50代の日本酒ファンへ
石川県白山市の吉田酒造店は、150年以上の歴史を持つ伝統ある酒蔵でありながら、常に時代の先を見据えた革新を続ける意欲的かつ革新的な酒造さんです。
霊峰白山の自然の恵みを最大限に活かし、伝統的な山廃仕込みからモダン山廃まで、多様な味わいの日本酒を生み出しています。
特に、地元産の原料にこだわり、環境に配慮した持続可能な酒造りへの真摯な取り組みは、これからの時代の酒蔵のあり方を示唆しています。
しっかりとした骨格と複雑な旨味を持つ「手取川」、軽やかでナチュラルな「吉田蔵u」。
どちらも、40代・50代の経験豊富な日本酒ファンの舌を唸らせるポテンシャルを秘めています。
ぜひ一度、吉田酒造店の酒を手に取り、その背景にあるストーリーや蔵人たちの情熱に思いを馳せながら、じっくりと味わってみてはいかがでしょうか。
きっと、新たな日本酒の魅力に出会えるはずです。
【関連記事】
石川県白山市、霊峰白山の麓に蔵を構える吉田酒造店。 この地で醸される銘酒「手取川」の中でも、春にだけ出会える特別な日本酒が「手取川 純米吟醸 生原酒 石川門」です。 地元石川県が誇る酒米「石川門」を100%使用し、搾りたてのフレッシュな味わいをそのまま瓶詰めしたこのお酒は、毎年多くの日本酒ファンを魅了しているお酒。 今回は、40代・50代のお酒好きな男女に向けて、実飲レビューを含めながら、その特徴、味わい、そして楽しみ方まで、詳しくご紹介していきます!
▶︎ 吉田酒造店の代表銘柄「手取川」はこちら >>
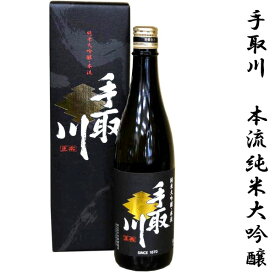
▶︎ 吉田酒造店の革新的銘柄「吉田蔵u」(モダン山廃)はこちら >>

▶︎ 「手取川」をふるさと納税でもらいたいならこちら >>

【こちらもオススメ】
\Amazon・nanaco・Pontaなら50円から換金可能 /\お得に食品ロス解消に役立てる/

▶︎ ロスオフは、食品ロスの支援をしながら、お得に商品を購入したい人にオススメ!






」:330年続く伝統と革新が生む、心に響く銘酒「仁勇」と「不動」の魅力-2-1024x683.png)





