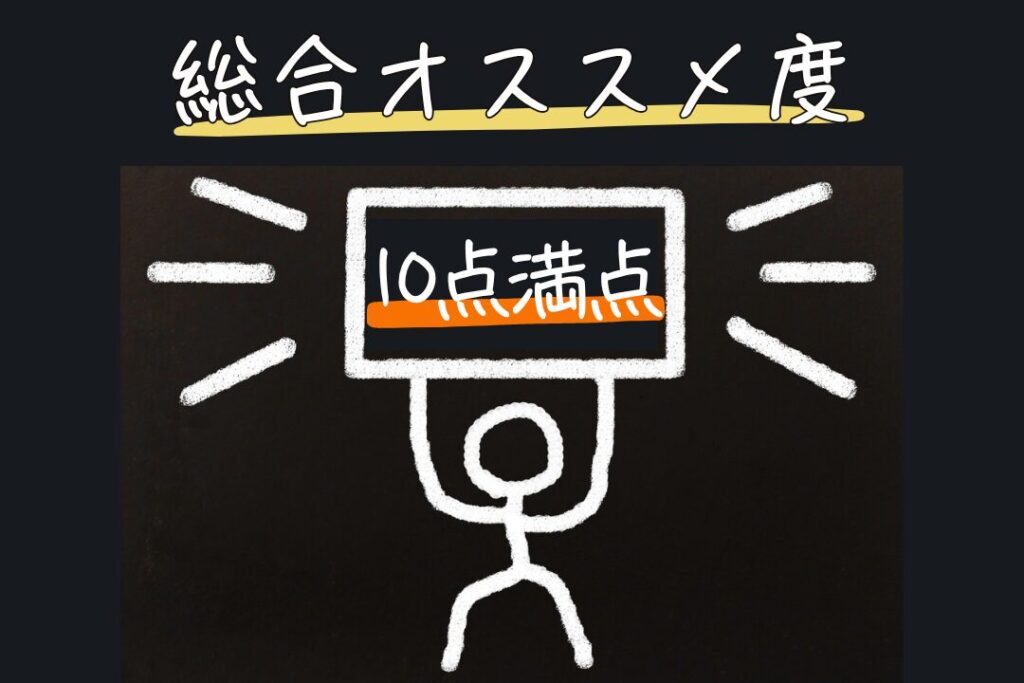日本酒の品質と個性を決定づける重要な工程の一つが「三段仕込み」です。この伝統的な製法は、日本酒造りの基本であり、多くの蔵元で採用されています。
本記事では、三段仕込みの具体的な工程から、他の仕込み方法との違い、それが日本酒の味わいにどのような影響を与えるのか、そして代表的な三段仕込みの日本酒とその実売価格に至るまで、詳細に解説していきます!
三段仕込みとは?日本酒造りの基本にして神髄
三段仕込みとは、日本酒の醪(もろみ)を造る過程で、酒母、麹、蒸米、水を4日間かけて3回に分けてタンクに投入する方法です。
この手法は、酵母の健全な増殖を促し、雑菌の繁殖を抑制することで、安定した発酵と高品質な日本酒造りを実現するために不可欠です。
なぜ三段階に分けて仕込むのか?
一度に全ての原料を投入すると、酒母中の酸が薄まり、酵母の増殖が追いつかなくなります。これにより、醪(もろみ)が酸性を保てなくなり、雑菌が繁殖するリスクが高まります。
三段仕込みは、原料を段階的に加えることで、酵母の活動を最適な状態に保ち、腐敗などのリスクを回避するための伝統的な知恵なのです。
三段仕込みの4日間の詳細な工程
三段仕込みは以下の4日間の工程で進められます。各工程にはそれぞれ名称と重要な役割があります。
初添(はつぞえ)/ 添仕込み(1日目)
酒母を入れたタンクに、初回分の蒸米、米麹、水を加えます。この量は醪全体の約15~20%程度が目安とされます。この段階で酵母が活動を開始し、発酵の基盤が作られます。
踊り(おどり)(2日目)
この日は原料の投入は行わず、酵母の増殖を促すために醪を休ませます。酵母が元気に活動し、次の仕込みに備える重要な期間です。
仲添(なかぞえ)/ 仲仕込み(3日目)
初添(1日目)の約2倍量の蒸米、米麹、水を加えます。これで仕込み量は全体の半分ほどになり、発酵がさらに活発になります。
留添(とめぞえ)/ 留仕込み(4日目)
仲添(3日目)の約2倍量の蒸米、米麹、水を加えます。これで三段仕込みの工程が完了します。この留添えの日を起点に、約3週間から1ヶ月かけてアルコール発酵が進み、日本酒が完成します。
三段仕込みのメリット:安定と品質の追求
三段仕込みは日本酒造りにおいて多くの利点をもたらします。
安定した発酵: 酵母の増殖を段階的に行うことで、健全な発酵環境を維持します。
雑菌汚染の防止: 醪の酸度を適切に保ち、雑菌の繁殖を抑制します。
温度管理の容易さ
段階的な投入により、醪の温度管理がしやすくなります。
バランスの良い酒質: 雑味が少なく、香り高く、繊細でバランスの取れた味わいを実現します。
三段仕込みと他の仕込み方法の比較
日本酒造りには、三段仕込み以外にも様々な仕込み方法があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
四段仕込み
四段仕込みは、三段仕込みが終わった後に、さらに蒸米・酒母・酒粕などを追加する方法です。これにより、糖分が増え、甘みのある日本酒になります。
カクヤスで販売されている「四段仕込」と名付けられた日本酒は、この製法の特徴を活かした商品です。
四段仕込みを超えた仕込み
四段仕込みを超えた仕込みも存在します。六段仕込みや八段仕込み、十段仕込みも存在します。それぞれ、三段仕込みの後に複数回原料を追加する方法です。例えば、六段仕込みでしたら、三段仕込み+3回蒸米・酒母・酒粕などを投入することを言います。
四段仕込み以上になればなるほど、糖分が残り、甘さが引き立つお酒となります。ただし、三段仕込みを超えて仕込んだお酒を美味しく造れるかどうかは難しいところがあり、基本的には三段仕込みとなります。
四段仕込み以上のお酒を例に挙げると、「千利休 純米大吟醸酒 八段仕込み 酣楽酒」があり、八段仕込みによって通常の日本酒にはない甘みやのど越しを実現したお酒となっています。
三段仕込み以外の仕込み方法とその特徴|まとめ
日本酒造りには三段仕込み以外にも仕込み方法が存在することがわかったと思います。先に紹介したものに加え、それらをアレンジした仕込み方法について次にまとめてみようと思います。
| 仕込み方法 | 特徴 | 味わいへの影響 |
| 三段仕込み | 最も一般的で基本的な仕込み方法。 | バランスが良く、繊細な味わい。 |
| 四段仕込み以上 | 三段仕込みの後、さらに蒸米などを追加投入する。回数が多いほど糖分が残りやすくなります。 | 甘みが強調される傾向がある。 |
| 再醸仕込み(貴醸酒) | 仕込み水の一部または全部に日本酒を使用する。一般的には留添えの際に日本酒を加える。 | 濃厚で甘酸っぱい、とろりとした味わい。デザート酒や食前酒に用いられる |
| 酵母仕込み(AY仕込み) | 酒母を造らず、初添の段階で培養酵母と乳酸を添加する。醸造期間の短縮と省力化が目的。 | 酒母を用いたものと遜色ない品質も可能だが、技術が必要。 |
| 液化仕込み | 酵素で米を液状化してタンクに投入する。高精白米の米粉(白糠)を利用することも。 | 発酵コントロールが容易。エコな側面も。 |
| スッポン仕込み | 初添から留添まで、全ての仕込みを同じ大きなタンクで行う。踊り分けの作業を省略。 | 温度管理が難しく、高級酒にはあまり用いられない。 |
これらの仕込み、それぞれが独自の味わいを生み出します。
日本酒って奥深いですね!
 Ryo
Ryo 仕込み方法毎に飲み比べてみるのも面白いよね!
三段仕込みの日本酒:味わいの特徴
三段仕込みで醸された日本酒は、酵母の働きが最大限に活かされ、雑味が少なくクリアな酒質になる傾向があります。
香りも穏やかで繊細なものが多く、米本来の旨味と甘みがバランス良く調和し、後味はスッキリとキレが良いのが特徴です。食中酒として優れたポテンシャルを持つお酒が多いです。
代表的な三段仕込みの日本酒と実売価格
三段仕込みは日本酒の基本製法であるため、日常的に楽しめる価格帯から超高級品まで、非常に多くの銘柄で採用されています。
日常的に楽しめる三段仕込みの日本酒 (目安)
楽天市場などのオンラインショップでは、三段仕込みで造られた日本酒が1,000円台から3,000円程度の価格帯で多数販売されています。
この価格帯では、普段の食事と共に楽しめる純米酒や本醸造酒、吟醸酒などが見つかります。
高級三段仕込み日本酒の例
以下は、特に高価格帯で知られる、三段仕込み(またはそれを基本とした高度な技術を要する)日本酒の例です。価格は変動する可能性があり、入手困難な場合もあります。
零響(れいきょう) -Absolute 0-
製造元:新澤醸造店(宮城県)
特徴:精米歩合0%台という驚異的な技術で醸される。クリアでシャープな味わい。
実売価格(目安):500ml 約385,000円
楯野川(たてのかわ) 純米大吟醸 光明(こうみょう)
製造元:楯の川酒造(山形県)
特徴:精米歩合1%を実現した日本初の酒。透明感のある究極の味わいを追求。
実売価格(目安):720ml 約116,000円
特別大吟醸 朱金泥能代 醸蒸多知(しゅこんでいのしろ かむたち)
製造元:喜久水酒造(秋田県)
特徴:兵庫県産山田錦を使用し、袋吊りで集めた雫を3年間熟成。年間生産本数も極僅か。
実売価格(目安):1,800ml 約110,000円

夢雀(むじゃく) 純米大吟醸
販売元:株式会社Archis(山口県)
特徴:伊勢神宮の「イセヒカリ」を使用。ヴィンテージ日本酒として長期熟成も可能。
実売価格(目安):750ml(新酒)約96,800円。熟成ヴィンテージ品は100万円を超えるものも存在。
純米大吟醸 楽聖(らくせい) 雄町米 一割五分磨き
特徴:雄町米を15%まで磨き上げた贅沢な逸品。芳醇な香りと深い味わい。
実売価格(目安):720ml 約55,800円
※上記価格は2025年5月現在の調査に基づくもので、変動する可能性があります。
まとめ
三段仕込みは、日本酒の安定した品質と豊かな味わいを実現するために、先人たちの知恵と経験によって確立された伝統的な醸造技術です。
4日間という時間をかけ、3段階に分けて原料を投入することで、酵母の働きを最適にコントロールし、雑菌の汚染を防ぎます。
この基本製法から、日常的に楽しめるものから世界の注目を集める超高級品まで、多種多様な日本酒が生み出されています。
日本酒を選ぶ際には、ぜひこの「三段仕込み」というキーワードにも注目し、その背景にある物語と共に味わってみてはいかがでしょうか。
【関連記事】